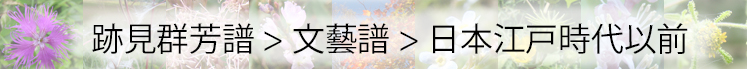
作者名 横井也有 (1702-1783) 作品名 「岐岨路紀行」、『鶉衣』拾遺中(有朋堂文庫本)所収 成立年代 延享二年(1745) その他
| 乙丑のことし、君にしたがひ奉りて、卯月六日江戸を出でて尾陽にのぼる。一年を恙なく歸國のけふを待ちえたるよろこび、人々も賀しあへるに、 卯花の中にうからぬ首途かな 年々なじみし武府の人々には、淺からず名殘をしまるゝもありて、流石に心ひかるゝ別とりどりなり。 麥の穗の睫もぬれてわかれかな 今年は木曾の山路を分くる也けり。仕官の身のならはし、心ならず馬槍のいかめしくさざめきつれたる、野老村童に事問まほしきも、物言ひかはさんはにげなき樣なれば、店の餅酒は見ぬ顏して過ぎ侍る。まことに風雅の本意ならぬもいかゞはせむ。こゝの山はとありて、かしこの川はかくありてと書き付けたらん、その所見ぬ人はさもおぼえぬ物にて、殊に筆の及ぶまじう、何の榮かあらん。たゞおもひよれる句ども少し筆にとむるのみ。 蕨(現蕨市)といへる所に、とばかり晝餉とゝのへて出づ。 われとむる手もなき夏の蕨かな 此夜上尾(現上尾市)に泊る。 七日 熊谷寺(現熊谷市仲町)に直實が像などあるよし、路のあわたゞしくて立ちよらず。 熊谷もはては坊主やけしの花 此夜本庄(現本庄市)に泊る。 八日 かくいへる所(高崎市倉賀野)にて くらが野ときけばや里も木下闇 けふは過ぐる道すがら、家々の軒に藤をさし侍り、花をもさし葉をもさせり。所の人にきけば、佛生會の手向也と云ふ。故郷にて見馴れぬ事也。陸奥國に花かつみふく類にやとめづらし。 灌佛もやがてはへとて藤の花 此夜板鼻(安中市板鼻)にとまる。 (以下、略) |
詠いこまれた花 ウツギ、麥、ワラビ、ケシ、フジ、マコモ
| 跡見群芳譜 Top | ↑Page Top |